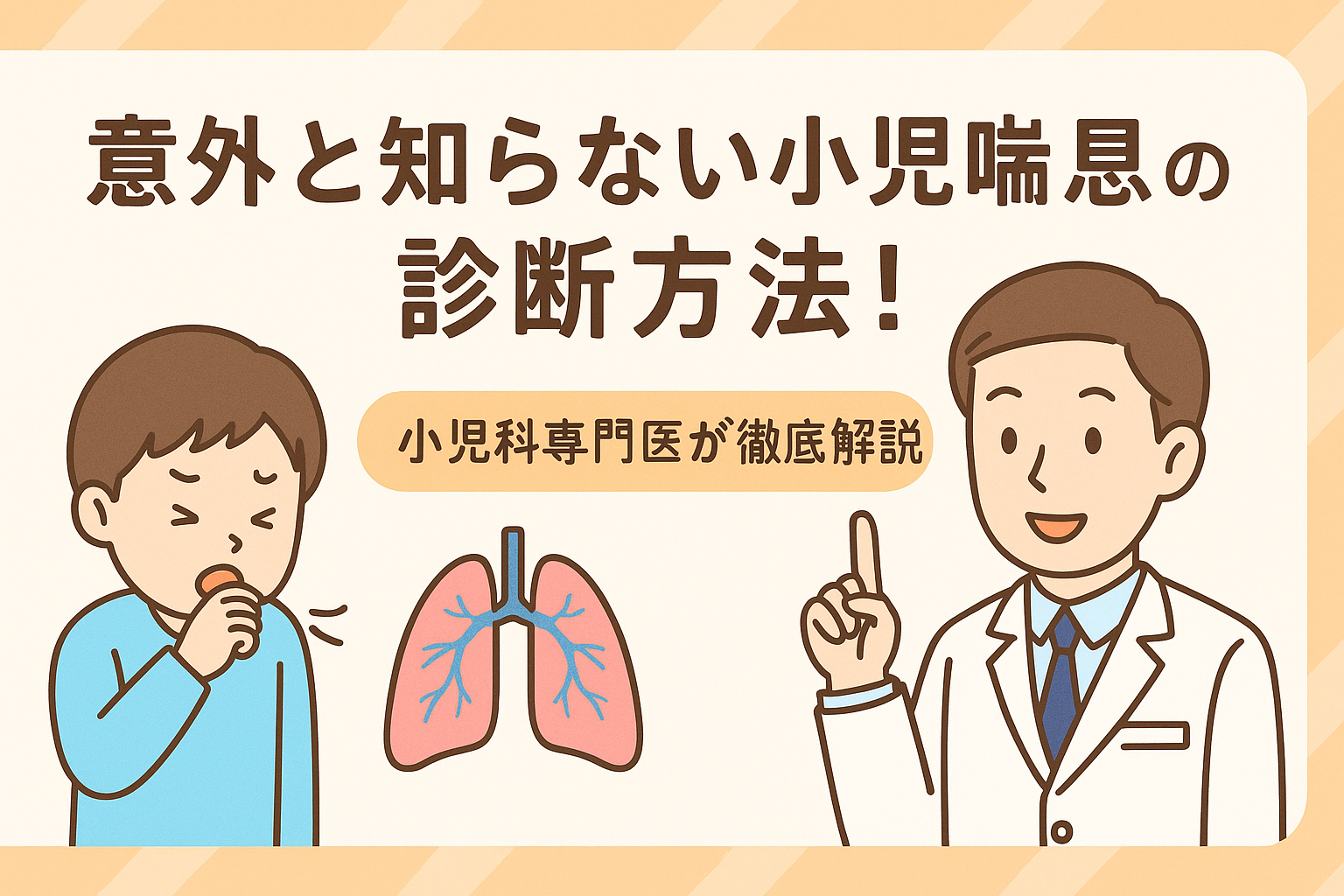目次
はじめに
前回の記事では、「小児喘息は治る病気」で、
子どもの喘息が大人とは違い、成長とともに改善していく可能性があることをお話ししました。
今回はその続編――テーマは「診断」です。
小児喘息の診断は、大人と比べてとても複雑です。
「検査をすればすぐに分かる」というものではなく、
症状の出方や時間帯、発作の回数、アレルギー体質など、
いくつものピースを組み合わせて診断していきます。
👉 小児科専門医でも慎重に見極める“難しい病気”です。
小児喘息の診断は「症状+検査+経過」で見極める
喘息は、気道(空気の通り道)が慢性的に炎症を起こして、
息をするたびにゼーゼー・ヒューヒューと音が出たり、咳が続く病気です。
診断ではこの「気道の炎症」と「過敏さ」を、
症状と検査の両方から確認していきます。
年齢が上がれば「検査」で見えることが増える
小学生くらいになると、協力して検査ができるようになります。
代表的なのが次の2つです。
🔹 ピークフロー(PEF)検査
息を思いきり吹き出して、空気の勢いを測る検査です。
専用のメーターに息を“フッ”と吹き込むだけで、
気道がどれくらい狭くなっているかをチェックできます。
- 数値が低い → 気道が狭くなっている
- 数値が安定 → 炎症が落ち着いている
毎日測定して記録しておくと、
「発作の予兆が出てきた」「治療がうまくいっている」など、
日々の変化を早めにキャッチできます。
👉 “見えない炎症”を、数値で見える化できる大切な検査です。
🔹 呼気一酸化窒素(FeNO)検査
息の中に含まれる「一酸化窒素(NO)」の量を測定し、
気道の炎症の強さを評価します。
数値が高いほど炎症が強く、
吸入ステロイドで治療を行うと数値が下がっていきます。
見た目ではわかりにくい炎症の状態を客観的に把握できるため、
診断だけでなく、治療の効果確認にも使われます。
👉 “咳が残っているけど炎症は?”を判断できる検査です。
乳幼児でも診断できる!3つのチェックポイント
乳幼児では、こうした検査がまだ難しいため、
症状のパターン・時間帯・アレルギー体質をもとに診断します。
🔸 1)くり返すゼーゼー(喘鳴)
風邪をひくたびにゼーゼー、ヒューヒューという音が出て、
治ってもまた繰り返す――
このような状態を3回以上くり返す場合は、小児喘息を強く疑います。
『小児気管支喘息治療・管理ガイドライン』でも、
「同様の発作性喘鳴を3回以上繰り返したら喘息を考慮する」
と明記されています。
👉 “一度きり”ではなく、“繰り返す”が診断のカギです。
🔸 2)咳の出る時間帯に特徴
小児喘息では、咳が夜間や明け方に多いのが特徴です。
特に、
- 寝入りばな(布団に入ってしばらくしてから)
- 明け方(起きる直前)
に咳が強く出やすい傾向があります。
夜中ずっと咳が続くわけではなく、決まった時間帯に集中して出るのがポイントです。
👉 夜間・明け方の咳は“気道の炎症が続いているサイン”。
🔸 3)アレルギー体質を調べる
小児喘息の多くは、アレルギー体質を背景に発症しています。
乳幼児でも採血でアレルギー検査を行うことができ、
- ダニ・ハウスダスト
- ペット(ネコ・イヌ)
- 花粉(スギ・ヒノキなど)
- カビ
といった**吸入アレルゲン(空気中のアレルギー物質)**に反応しているかを調べます。
もし陽性であれば、喘息やアトピーなどアレルギー関連の疾患を起こしやすい体質と考えられ、
診断を後押しする重要な手がかりになります。
さらに、結果をもとに家庭内の環境整備(寝具・掃除・ペット対応など)を行うことで、
発作の回数を減らすことも可能です。
👉 「何に反応しているか」を知ることが、予防にもつながります。
小児科専門医でも迷うことがある
乳幼児では、RSウイルスやヒトメタニューモウイルスなど、
喘息に似たウイルス感染による咳が多く見られます。
このため、症状だけで「喘息」と決めつけるのは難しく、
医師は発作のパターンや経過を時間をかけて観察します。
👉 すぐに診断がつかなくても大丈夫。確実に見極めることが大切です。
ご家庭でできるサポート
診察時に役立つのは、親御さんの「観察」と「記録」です。
- 咳やゼーゼーの出た日・時間帯・きっかけをメモする
- 咳やゼーゼー音の動画をスマホで撮っておく
- アレルギー検査の結果を保管し、診察で共有する
👉 日常の記録が、正確な診断を支える一番の材料になります。
まとめ
- 小児喘息は、症状+検査+経過で診断する病気
- 年長児では ピークフロー・呼気NO などの検査が有効
- 乳幼児では 発作のくり返し・時間帯の特徴・アレルギー体質 から総合的に診断
- アレルギー検査は乳幼児でも可能で、環境整備にも役立つ
- 小児科専門医でも慎重に経過を見て判断する
親御さんへのメッセージ
小児喘息の診断は、「一度で分かる病気」ではありません。
お子さんの体の中で起きていることを、少しずつ“見える形”にしていく――
それが診断の第一歩です。
👉 焦らず、観察を続けることが“確かな診断”への近道。
医師と一緒に、安心できる答えを見つけていきましょう。