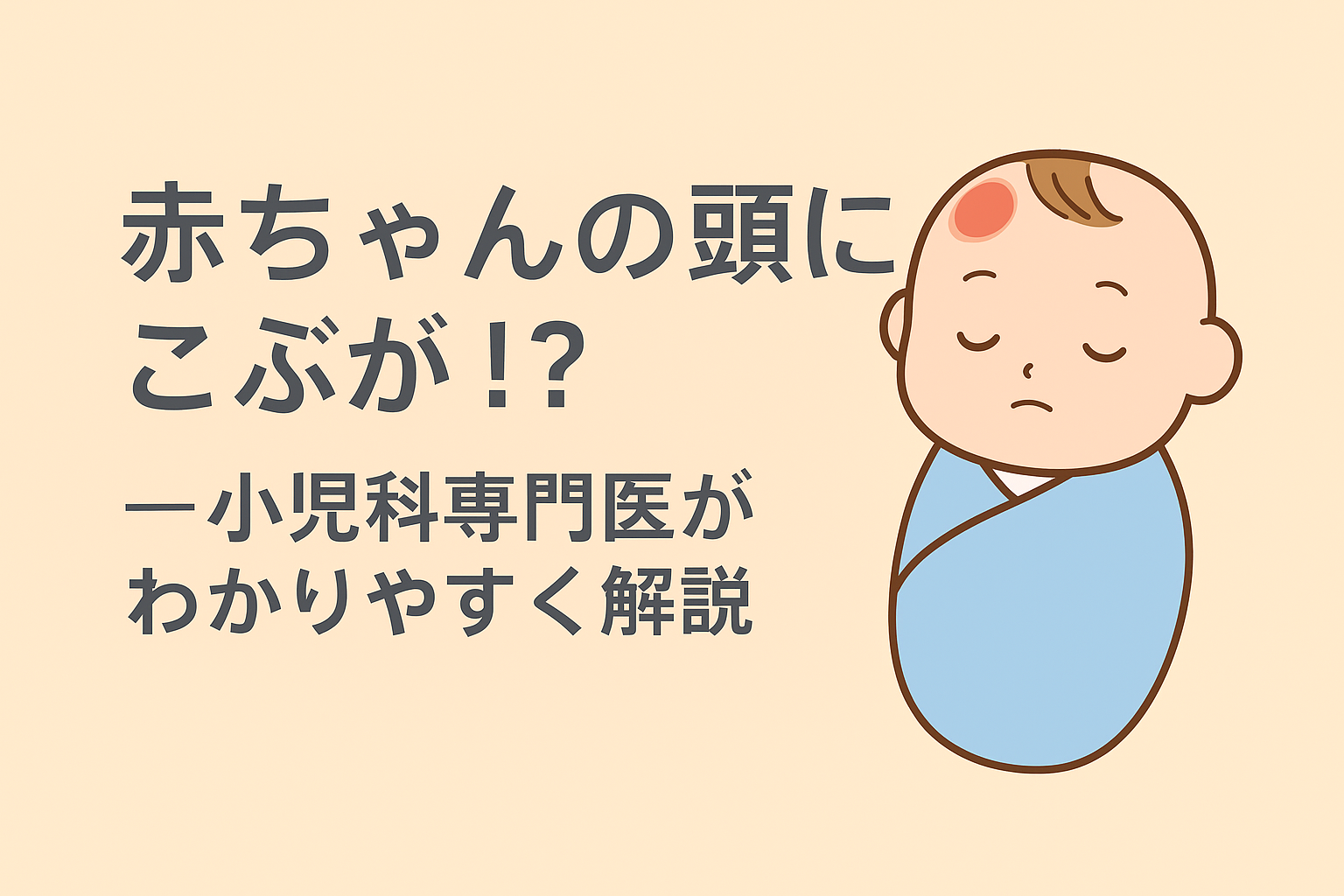目次
はじめに
赤ちゃんが生まれたあとに、頭のてっぺんや横に“こぶ”のようなふくらみが見られることがあります。
「ぶつけたの?」「出産のときのケガ?」と驚く親御さんも多いですが、
その多くは分娩時の圧迫による一時的な変化です。
ほとんどは自然に治るものですが、中には注意が必要なものもあります。
今回は、小児科専門医の立場から「赤ちゃんの頭のこぶ」について解説します。
🩺 よくある3つのタイプ
赤ちゃんの頭にできる“こぶ”には、大きく分けて次の3つがあります。
① 産瘤(さんりゅう)
出産時、赤ちゃんの頭が産道を通るときの圧で、皮下にむくみ(浮腫)ができたものです。
・境界がはっきりせず、全体がふんわり腫れて見える
・触ると柔らかく、粘土のように少しへこむ感触
・出生直後から見られ、1〜2日で自然に消失
👉 もっともよく見られる“こぶ”で、特別な治療は不要です。
② 頭血腫(ずけっしゅ)
頭の骨を覆う「骨膜」という膜が剥がれて、その下に出血がたまった状態です。
・吸引分娩や鉗子分娩で起きやすい
・境界がはっきりしていて、水が入ったヨーヨーのような感触
・生後数時間〜2〜3日で大きくなり、1〜3か月でゆっくり吸収
・吸収の過程で黄疸(皮膚の黄ばみ)が長引くことも
👉 通常は経過観察でOK。ただし、大きい場合は時間をかけてしっかり治ります。
③ 帽状腱膜下血腫(ぼうじょうけんまくかけっしゅ)
頭の広い範囲を覆う「帽状腱膜」という膜の下で出血が起きた状態です。
・吸引や鉗子分娩のあとに発症することが多い
・頭全体がぶよぶよと腫れていて、境界が不明瞭
・額やまぶた、耳のまわりまで腫れが広がることも
・出血量が多い場合は貧血やショックを起こす危険性もある
👉 まれですが命に関わることも。疑われたらすぐに受診を。
🧩 経過と見守り方
多くの“こぶ”は自然に小さくなります。
しかし、以下のような場合は医師の診察が必要です。
- こぶが日に日に大きくなる
- 3か月以上たっても残っている
- 泣くとこぶが大きくなる、拍動する
- 顔色が悪い、元気がない、黄疸が強い
これらの場合、頭の中に出血が広がっている・骨折・血が固まりにくい体質などが隠れている可能性があります。
頭部エコーやCTなどで詳しく調べることがあります。
👉 「だんだん小さくなる」は良いサイン。反対に「大きくなる」「変化しない」は相談のサインです。
🧠 頭の骨や脳への影響は?
多くの赤ちゃんでは、頭の形や発達への影響はありません。
頭血腫のあとに一時的に骨の縁が盛り上がって「火山のクレーターみたい」と感じることがありますが、
これは吸収の過程で一時的に見られる変化です。数か月で自然に目立たなくなります。
👉 骨が盛り上がるのも治っていく途中のサイン。心配しすぎなくて大丈夫です。
🚼 家でできるケア
・頭を強く押したり、マッサージしたりしない
・湯あがりやタオルで拭くときも優しく触る
・“こぶ”を冷やす必要はありません
・発熱・ぐったり・黄疸の悪化があれば受診
👉 「触らない・いじらない・様子をみる」が基本。気になるときは写真で記録しておくのも◎
まとめ
・赤ちゃんの“こぶ”の多くは、出産時の圧迫による一時的なものです。
・産瘤は1〜2日、頭血腫は1〜3か月で自然に治ることがほとんど。
・帽状腱膜下血腫はまれですが重症化のリスクがあるため、早めの受診を。
・強く触らず、見守る姿勢が大切です。
👉 赤ちゃんの“こぶ”は、がんばって生まれてきた証のひとつ。
時間とともに落ち着いていく姿を、やさしく見守ってあげましょう。