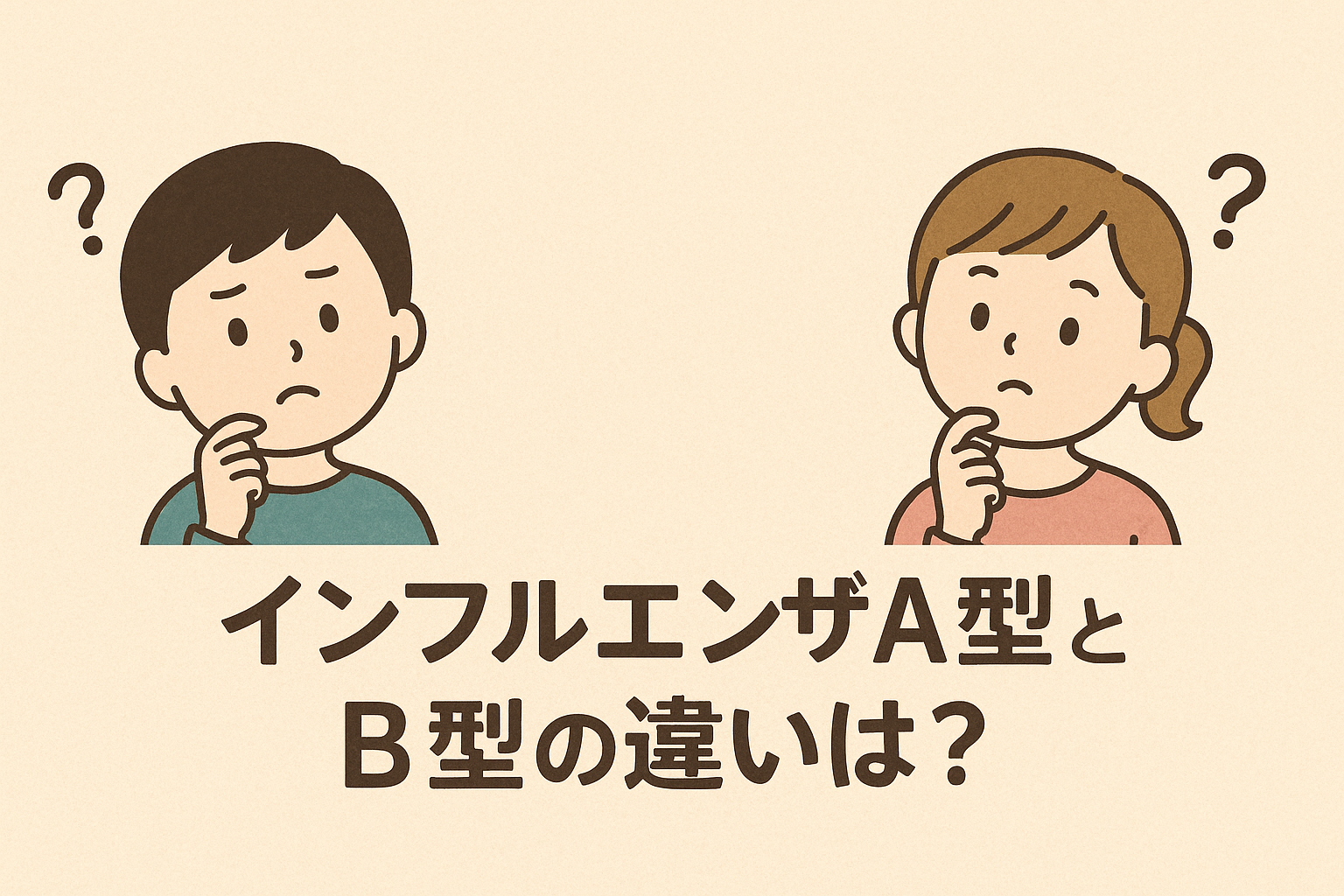冬にかけて流行するインフルエンザ。
「A型です」「B型ですね」と診断を受けたことがある方も多いのではないでしょうか?
果たしてこの型の違いにどんな意味があるのでしょうか?疑問に思ったことがある方も多いはず。
今回は、インフルエンザA型・B型の違いや特徴について、小児科専門医の目線で解説します。
インフルエンザA型とは?
インフルエンザA型は、もっとも感染力が高く、重症化しやすいのが特徴です。
ウイルス自体が変異を起こしやすく、毎年少しずつ姿を変えるため、一度かかっても翌年また感染することがあります。
ヒト以外にも鳥や豚などの動物にも感染し、大流行(パンデミック)を起こす可能性があるのもA型の特徴です。
症状としては、
- 38〜40度の高熱
- 咳・喉の痛み
- 頭痛・倦怠感
- 関節痛・悪寒
など、全身の強い症状が出やすく、小さな子どもや高齢者では肺炎や脳症などの合併症にも注意が必要です。
👉 高熱+全身症状が強い場合はA型の可能性が高く、早めの受診を。
インフルエンザB型とは?
インフルエンザB型は、A型ほど急激な症状は少ないものの、発熱や咳が長引きやすい傾向にあります。
感染はヒトのみに起こり、変異型が少ないため、A型に比べて流行の規模はやや小さめです。
主な症状としては、
- 38度前後の発熱
- 咳、喉の痛み
- 下痢や嘔吐などの消化器症状
が見られ、A型よりもお腹の症状を伴うことが多いのが特徴です。
また、流行時期がやや遅れて春先~夏にかけても発症することがあります。
👉 発熱が長引く、下痢や嘔吐を伴う場合はB型の可能性も。
A型とB型の関係性
A型にかかった人でも、その後にB型にかかることはあります。
A型とB型は異なるタイプのウイルスであり、どちらかに感染してももう一方への免疫はできません。
病院で使うインフルエンザの検査キットでは、A型かB型かまで判定できるものが主流です。
小児科医としての臨床経験から言うと、
「A型が流行してからB型が流行してくる」というのが毎年の定番パターン。
検査でB型が出はじめると、
「ああ、そろそろインフルのシーズンも折り返しかな」と感じることが多いです。
👉 一度A型を発症したあとも、B型の流行には油断しないようにしましょう。
A型とB型の違いまとめ
| 特徴 | インフルエンザA型 | インフルエンザB型 |
|---|---|---|
| 感染対象 | ヒト+動物 | ヒトのみ |
| 流行時期 | 11月〜3月(冬) | 11月〜3月(冬)〜春・夏にかけて |
| 症状の強さ | 強い(高熱・全身倦怠感) | 比較的軽い・消化器症状あり |
| 再感染 | 起こりやすい(変異しやすい) | 変異少なく再感染しにくい |
| 重症化 | あり(肺炎・脳症など) | まれ |
対応・登園(登校)について
インフルエンザの出席停止期間は、
発症した後5日経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまでが目安です。
出席停止期間については過去にまとめた記事があるのでそちらも参考にしてみてください
⇒出席停止ってどう決まるの?― 小児科専門医が解説する「登園・登校の目安と対応」
ただし、園や学校ごとに細かいルールを設けている場合もあるため、
医師の診断+園・学校の方針に従って決めていくことが大切です。
👉 インフルエンザA型・B型で治療や予防法が特別に異なることはありません。
治療についてはこちら⇒小児のインフルエンザ治療はどう選ぶ? ― 小児科専門医がわかりやすく解説
まとめ
- A型は感染力・重症化リスクが高い
- B型は長引く+消化器症状が多い
- A型にかかったあとでもB型にかかることはある
- A型・B型で治療法・予防法の基本は同じ
- 登園・登校は医師+園のルールを確認してから
👉 高熱や倦怠感が強いときは無理せず早めに受診を。
家庭内でもマスク・手洗い・換気を徹底し、次の流行波に備えましょう。