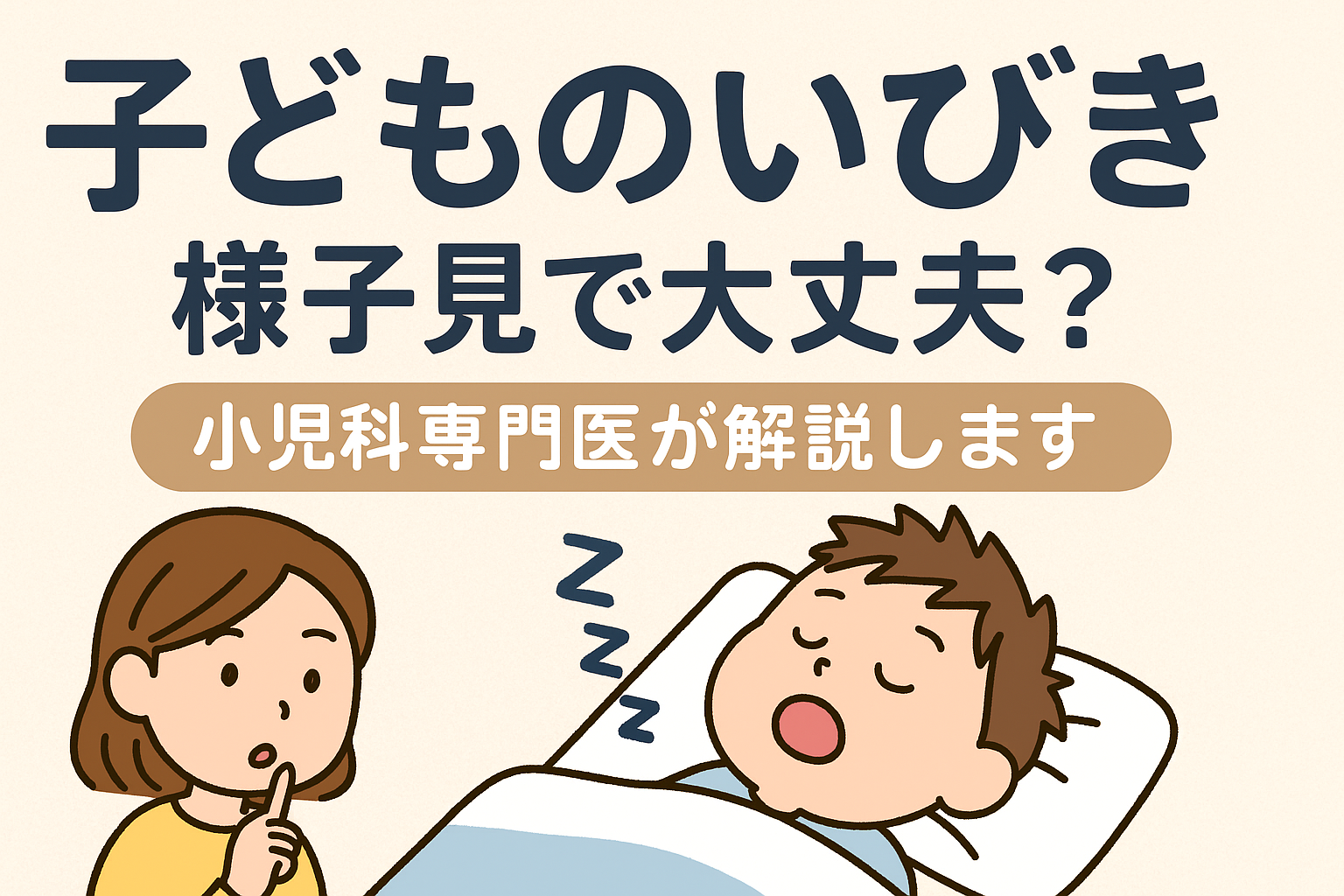はじめに
「寝ているときに、子どもがいびきをかいている」――そんな相談は実はとても多く、就学前後のお子さんの約1~2割でみられます。
多くは鼻づまりなどによる一時的なものですが、なかには**「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)」**という、放置すると発達や学習に影響を及ぼす病気が隠れていることもあります。
いびきが続くと、眠りが浅くなり、成長ホルモンの分泌が妨げられることがあります。
また、集中力の低下や日中の眠気、落ち着きのなさといった行動面にも影響することが知られています。
👉 子どものいびきは、“体からの小さなサイン”として注目してあげましょう。
子どものいびきの原因
子どものいびきは、気道(鼻からのどまでの空気の通り道)が狭くなることで起こります。
代表的な原因には以下のようなものがあります:
- アデノイド(咽頭扁桃)や口蓋扁桃の肥大
→ 子どものいびきの約7割がこの原因といわれます。6歳前後で自然に大きくなり、鼻呼吸を妨げることがあります。 - アレルギー性鼻炎や慢性鼻炎
→ 鼻づまりが続くと口呼吸になり、気道の抵抗が増えていびきをかきやすくなります。 - 肥満や顎が小さい骨格的特徴
→ 気道が圧迫されて狭くなりやすく、無呼吸が残存・再発しやすい傾向も。 - 風邪や一時的な鼻汁・咽頭炎
→ 一過性のいびきの多くはこのタイプで、数日で落ち着くことがほとんどです。
👉 数日でおさまるいびきは心配いりませんが、毎晩続くようなら原因を調べましょう。
こんなサインがあれば注意を
以下のような症状がみられる場合は、早めに医療機関で相談することをおすすめします。
- 毎晩のように大きないびきをかく
- 寝ている途中で呼吸が止まる
- 胸やお腹がへこむような「苦しい呼吸」をしている
- 寝相が極端に悪い、または夜尿(おねしょ)が増えた
- 朝すっきり起きられない、日中ぼんやりしている
- 口をぽかんと開けて寝ている
これらは**閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)**の可能性があります。
睡眠中の酸素不足は、成長ホルモン分泌や脳の発達にも関係すると報告されています。
👉 「週3回以上のいびき」や「夜間の呼吸の乱れ」がある場合は、動画を撮って相談してみましょう。
診断の進め方
診察では、まず耳・鼻・のどの状態をすべてチェックして原因を推定します。
扁桃肥大やアデノイド肥大が疑われる場合には、レントゲンや内視鏡で上咽頭のスペースを確認します。
また、家庭での観察も非常に大切です。
いびきをかいているときの動画や、呼吸の止まり方を記録しておくと診断の手がかりになります。
必要に応じて「終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)」という専門検査を行い、1時間あたりの無呼吸や低呼吸の回数(AHI)で重症度を評価します。
ただし、子どもでは検査が難しいことも多く、簡易検査や経過観察を組み合わせる場合もあります。
👉 寝ている間の様子は、家庭でしかわからない“大切な情報”です。記録して見せるだけでも診断の助けになります。
治療と対応
原因や重症度により、治療法は異なります。
🔹 軽症の場合
- アレルギー性鼻炎や鼻づまりの治療を行い、鼻呼吸を促します。
- 鼻噴霧用ステロイドや抗ロイコトリエン薬が有効なこともあります。
🔹 中等症~重症の場合
- 手術(アデノイド切除術や口蓋扁桃摘出術)を行うことで、多くの症例でいびきや無呼吸が改善します。
- 手術により夜尿(おねしょ)が減ったり、集中力・成長スピードが改善する例も報告されています。
- ただし、肥満児や顎が小さいタイプでは再発のリスクがやや高いため、生活習慣の見直しも重要です。
👉 軽症ならまず鼻づまり治療を、改善が乏しい場合は耳鼻科での相談を。
アレルギーとの関係
アレルギー性鼻炎や花粉症などがある子どもでは、睡眠の質が低下しやすく、いびきや口呼吸が長引くことがあります。
鼻づまりを放置すると、気道の狭窄が続いて無呼吸が悪化することも。
👉 季節的に鼻が詰まりやすい子は、早めに鼻炎治療を始めて“いびきの悪循環”を断ちましょう。
🩺 まとめ
- 子どものいびきの多くは扁桃・アデノイド肥大や鼻づまりが原因。
- 「毎晩のいびき」「夜間の呼吸停止」「日中の集中力低下」がある場合は要注意。
- 成長ホルモン分泌や学習への影響が出ることもあります。
- 軽症はいびき治療・鼻炎対策から、重症は手術で改善することが多い。
- 肥満児では再発しやすいため、生活習慣の見直しも大切。
- スマホで動画を撮って受診時に見せるのも有効。
👉 いびきは“眠りの質”のサイン。
放っておかず、気になるときは早めに相談してあげてください。