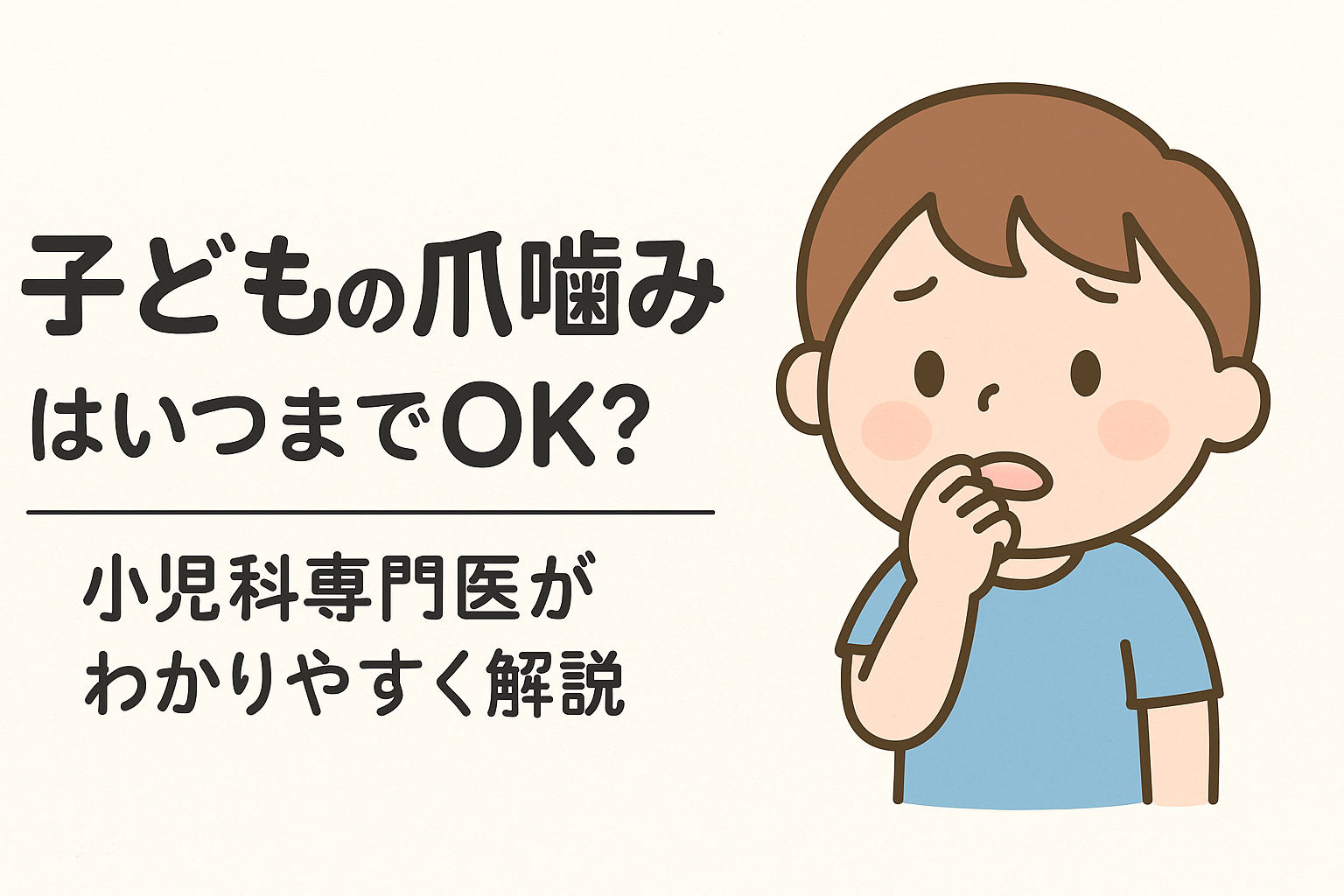目次
はじめに
爪を噛むのは「悪い癖」と思われがちですが、子どもの場合は発達や心のバランスと深く関係しています。
3〜5歳ごろから見られ、ほとんどは成長とともに自然に減少します。
とはいえ、出血するほど噛んでいたり、なかなかやめられない場合は注意が必要なこともあります。
今回は、子どもの爪噛みの原因や対応法について、小児科専門医の視点からわかりやすく解説します。
🪞 爪噛みの原因
爪を噛む行為(咬爪症)は、手持ち無沙汰・不安・緊張など、心理的なきっかけで始まることが多いとされています。
特に、
- 幼稚園や小学校への入園・進学
- きょうだいの誕生などの家庭環境の変化
- 新しい友達関係への不安
がきっかけになることもあります。
また、内向的・神経質・緊張しやすいタイプの子に多い傾向があり、
発達特性(こだわりが強いなど)と関係している場合もあります。
爪噛みそのものよりも、その背景にある気持ちや環境に目を向けることが大切です。
👉 爪噛みは「不安」や「集中」など、気持ちのバロメーターのような行動です。
🩹 爪噛みで起こりうるトラブル
多くの子どもでは自然に改善しますが、強く噛みすぎると次のような問題が生じることがあります:
- 爪が不自然に短くなる・ギザギザになる
- 甘皮をはがして出血する
- 爪の変形や根元の炎症
- まれに骨髄炎などを起こすケースも報告あり
ただし、出血や痛みを伴わない範囲であれば経過観察で十分なことがほとんどです。
叱ったり無理にやめさせようとするのは逆効果になることもあります。
👉 出血していなければ、焦らず見守る姿勢が大切です。
🌱 ご家庭でできる対応
1. 無理にやめさせない
「やめなさい」と叱ると、かえって緊張や不安を強めてしまいます。
やめさせるよりも「どうして噛んでいるのか」に目を向けてあげましょう。
👉 注意よりも、共感の言葉をかけてあげましょう。
2. ほめて伸ばすアプローチ
爪を噛まずにいられた時間をカレンダーに記録したり、
「今日は頑張ったね」と声をかけるなど、達成感を大切にする方法が効果的です。
👉 小さな“できた!”を積み重ねることで自然と習慣が変わっていきます。
3. 苦味のあるマニキュアも一案
市販の「バイター・ストップ」など、苦味成分を含む透明コートを塗る方法もあります。
毎日塗布することで噛みにくくなり、軽症例では有効です。
ただし、本人にやめたい意志がないと続けにくいため、本人の気持ちを尊重しましょう。
👉 道具は「本人がやめたい」と思ったタイミングで使うのがポイント。
4. 環境や気持ちへのサポート
環境の変化がきっかけの場合、家庭内で安心できる時間を増やすことも大切です。
「甘えたい」「不安だな」という気持ちの表現が爪噛みになっている場合もあります。
👉 たくさん甘えさせてあげることも、立派な“治療”のひとつです。
🧭 受診の目安
- 出血や感染を繰り返す
- 爪の形が変形している
- 他にもチックや夜驚などの癖が見られる
- 学校生活に支障が出るほど強いストレスがある
このような場合は、小児科や皮膚科に相談を。
また、発達特性やこだわりが強い場合は発達相談を検討しましょう。
👉 一人で抱えず、気になるときは医師に相談を。
まとめ
- 爪噛みは「悪い癖」ではなく、子どもなりの気持ちを整理する手段のひとつ。
- 成長とともに自然に減っていくことが多く、焦って無理にやめさせる必要はありません。
- 出血していなければ、叱らずに見守ることが大切です。
- 「やめさせる」よりも、「安心できる環境を整える」ことを意識しましょう。
- 少しずつ噛まない時間が増えてきたら、たくさん褒めてあげることが自然な卒業への第一歩です。
👉 爪を噛まない日が少しずつ増えたら、たくさん褒めてあげましょう。
小さな達成感が、自然な卒業につながります。