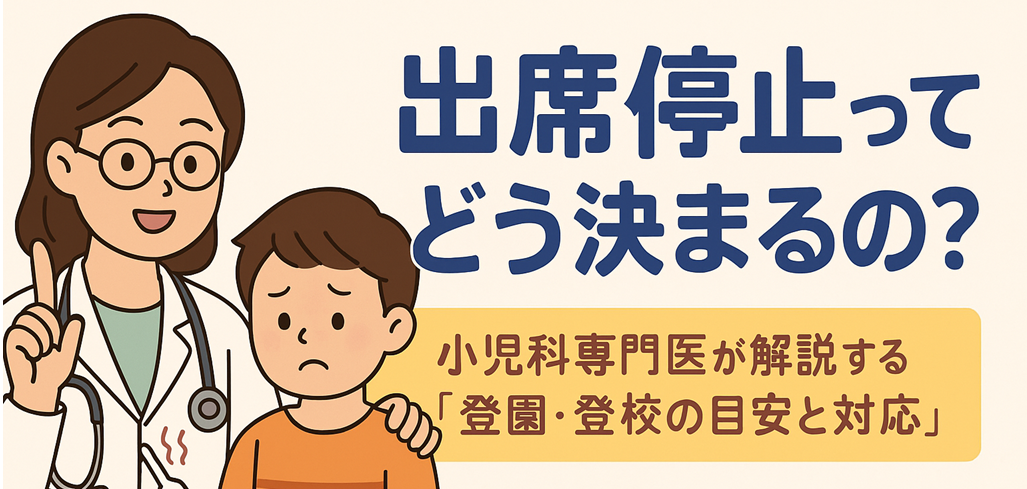目次
はじめに
「熱が下がったけど、もう保育園に行っていいの?」「“出席停止”って何日休めばいいの?」
お子さんの体調が回復してきたころに、こんな疑問を感じたことはありませんか?
実はこの“出席停止”という仕組みは、学校保健安全法という法律に基づいています。
ただし、実際の判断は一律ではなく、感染症の種類・お子さんの回復の程度・家庭や園の事情によって柔軟に行われています。
出席停止の目的と考え方
出席停止は「病気が治るまで家で休ませる制度」ではなく、
感染力が十分に低下して他の子にうつさなくなるまで休む仕組みです。
学校保健安全法では、感染症を以下のように分類しています。
| 分類 | 主な対象 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 第1種 | コレラ、赤痢など重篤な感染症 | 医師・保健所が中心に判断 |
| 第2種 | インフルエンザ、水ぼうそう、おたふくかぜ、麻しん、風しんなど | 法律で出席停止期間が明示 |
| 第3種 | 溶連菌感染症、咽頭結膜熱(プール熱)など | 医師の診断をもとに園・学校と判断 |
| その他(第4種相当) | 感染性胃腸炎、RSウイルスなど | 学校医・園長判断で柔軟に対応可 |
👉 出席停止期間は「完治」ではなく「感染させないこと」が目的。
回復が早くても、まだ感染力がある時期には登園できません。
感染症ごとの目安(主なもの)
| 病気名 | 出席停止の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 発症後5日、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過 | 熱が下がってもすぐは登園不可 |
| 水ぼうそう | すべての発疹がかさぶたになるまで | 乾いた発疹はうつらない |
| おたふくかぜ | 耳下腺などの腫れが出てから5日、かつ全身状態が良い | 反対側が腫れても日数はリセットしない |
| 麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過 | 修飾麻しんでは診断が難しいことも |
| 風しん | 発疹が消えるまで | 妊婦への感染に注意 |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消えて2日を経過 | 目の充血が残る間は感染力あり |
| 溶連菌感染症 | 抗菌薬を始めて24時間以上経過 | 治療を中断すると再燃しやすい |
| 感染性胃腸炎(ノロ・ロタなど) | 嘔吐・下痢が治まり、食事がとれる | 便中にウイルスが残るため衛生管理を継続 |
| RSウイルス | 咳が落ち着き、全身状態が良好であれば登園可 | 回復に時間がかかる場合もあり |
登園・登校の判断は“医師+園や学校のルール”で決まることもあります
感染症によっては、「○日休む」と明確に決まっているもの(例:インフルエンザ、水ぼうそうなど)もありますが、
中には、園や学校ごとに独自のルールを設けている場合もあります。
たとえば、ある園では「咳が残っていても元気なら登園OK」、
別の園では「咳が完全に止まるまで登園不可」といった違いが見られます。
そのため実際には、
- 医師の診察結果
- お子さんの回復の様子
- 園・学校が定める登園基準
この3つをもとに、医師と園・学校のルールに従って判断していくことになります。
👉 「熱が下がったし大丈夫かな?」と思っても、
まずは医師の意見や園の基準を確認しておくと安心です。
家庭で気をつけたいこと
出席停止の間は、ただ“登園できない期間”ではなく、
子どもがしっかり回復するための時間でもあります。
- 休養を優先:熱が下がっても無理は禁物。睡眠を十分に。
- 水分補給:発熱や下痢時は水・お茶・経口補水液をこまめに。
- 食事は食べられるものから:消化のよい食事を。食欲が戻ることが回復のサイン。
- 兄弟への感染防止:タオルの共用やお風呂の同時入浴は避ける。
- 再登園時の情報共有:家庭での経過を園・学校に伝えると安心。
👉 休むことも治療の一部。「早く治すために休む」と考えましょう。
よくある質問
Q1. 「治癒証明書」は必ず必要?
多くの園や学校では、「登園許可書」「治癒証明書」を求める場合があります。
しかし、実際には法的義務はありません。
学校保健安全法では、「医師が感染の恐れがないと認めたとき」は登園可能とされています。
園や学校ごとに対応が異なるため、事前に方針を確認しておくとスムーズです。
Q2. 出席停止期間を短くしてもいいの?
症状が改善し、医師が「感染力がない」と判断した場合は、
基準期間を待たずに登園しても問題ありません。
一方で、体力が戻っていないと再発しやすいため、
「登園できる=全快」ではないことを忘れずに。
まとめ
- 出席停止は「感染力がなくなるまで」の目安であり、「完治まで休む制度」ではない。
- 感染症の種類によって法律で目安が示されているが、主治医・学校医の判断で柔軟に対応可能。
- 家庭では回復を見守りながら、感染拡大を防ぐ生活習慣を続けることが大切。
- 不安な時は「早めの相談」が一番の安心材料です。
👉 出席停止は“休ませる制度”ではなく、“安心して戻るための制度”。焦らず、子どもの元気を最優先に考えましょう。