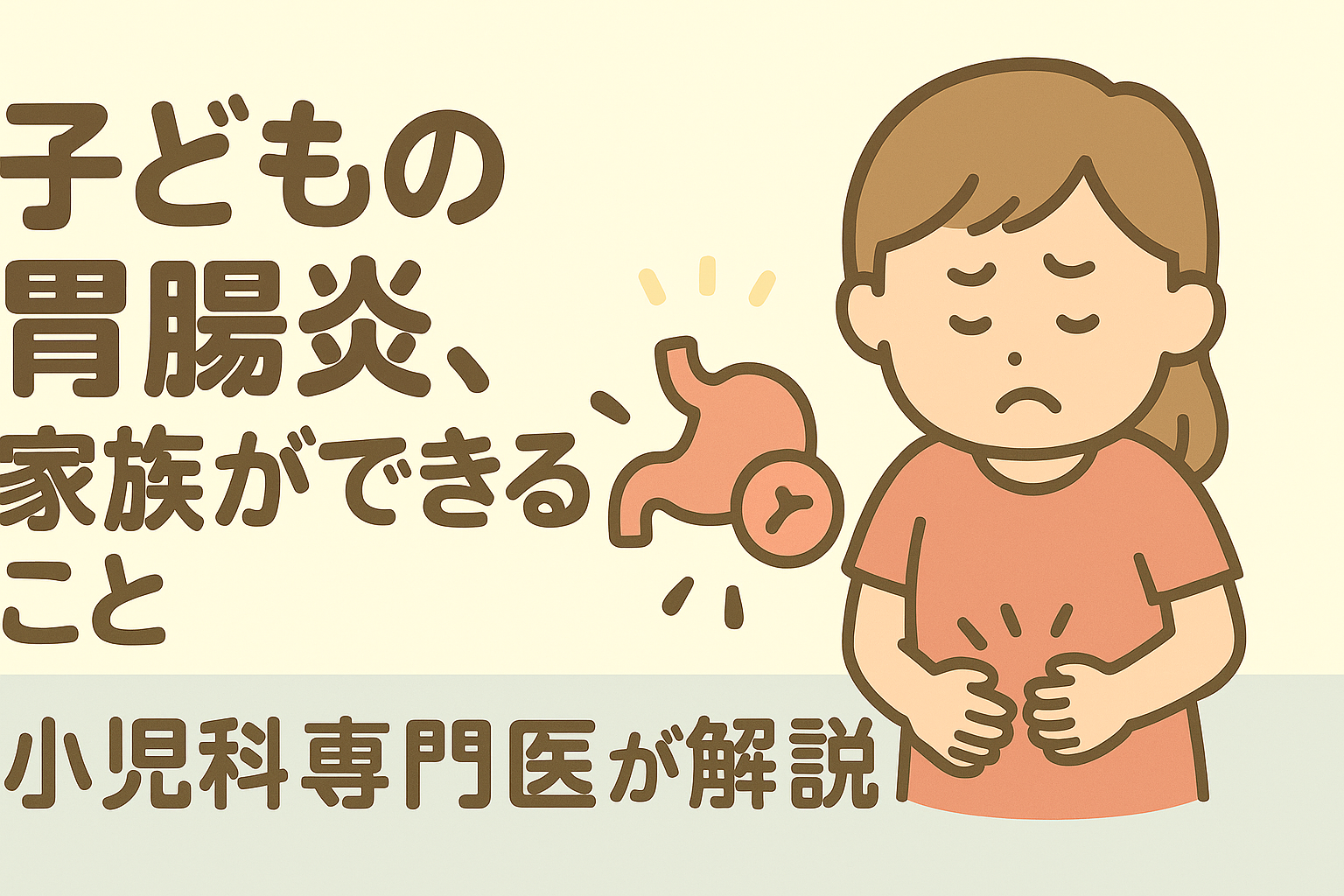目次
はじめに
保育園や家庭で「急に吐いた」「下痢が止まらない!」と慌てること、ありますよね。
その多くはウイルス性胃腸炎です。
冬場のノロウイルス、春先のロタウイルス、通年性のアデノウイルスなどが代表的な原因。
感染力がとても強く、兄弟や家族に広がることも少なくありません。
👉 胃腸炎は“慌てず・焦らず・脱水予防”。まずは落ち着いて見守ることが大切です。
胃腸炎とは
ウイルスや細菌などが胃腸に感染して炎症を起こす病気です。
子どもの場合、そのほとんどはウイルス性で、抗菌薬(抗生物質)は必要ありません。
主な症状は
- 嘔吐
- 下痢(水っぽい便)
- 発熱
- 腹痛や食欲の低下
多くは数日で自然に治りますが、特に脱水には注意が必要です。
主な原因ウイルスと特徴
🔸 ノロウイルス
- 流行時期:冬(11〜3月)
- 特徴:突然の嘔吐から始まり、発熱や軽い下痢を伴う
- 感染力:極めて強い(わずかなウイルス量でも感染)
- 感染経路:接触・飛沫・食品(カキなど)
吐物や便の処理時は手袋・マスクを使用し、塩素系漂白剤で消毒を。
アルコールでは不十分なことがあります。
👉 ノロは「家庭内感染対策」が最重要。吐物処理は丁寧に。
🔸 ロタウイルス
- 流行時期:冬〜春
- 特徴:白っぽい下痢・強い嘔吐・発熱。時にけいれんを伴う
- 重症化リスク:脱水が強く、入院が必要になることも
- 予防:ロタワクチン(生ワクチン)で重症化を防げる
ワクチンの普及で重症例は大きく減少しています。
生後6週から接種可能で、現在は定期接種(公費)になっています。
👉 ワクチンで守れる病気。早めの接種が安心です。
🔸 アデノウイルス(腸管型)
- 流行時期:通年(やや夏に多い)
- 特徴:発熱が長引き、下痢が1週間以上続くことも
- 感染経路:接触感染(手指やタオルの共有でうつる)
アデノウイルスは咽頭炎や結膜炎の原因にもなりますが、同じアデノウイルスでも型によって症状は異なり、腸管型(40・41型)が胃腸炎を起こします。
👉 「熱が長く続く+下痢」の組み合わせではアデノ腸炎を疑いましょう。
診断と治療
診断は症状と流行状況から行い、便検査でウイルスを特定できる場合もあります。
ただし、どのウイルスかを調べても治療内容は変わりません。
一番大切なのは脱水を防ぐことです。
ご家庭での対応
🔹 水分補給
- 吐き気があるうちはスプーン1杯ずつ経口補水液を
- 嘔吐が落ち着いたら、少しずつ量を増やしていく
- 哺乳児は母乳・ミルクもOK(回数を増やしてこまめに)
👉 「飲めるか・出ているか(おしっこ)」が回復のサイン。
🔹 食事の工夫
胃腸炎のとき、厳しい食事制限は不要です。
本人が食べたがるものを、無理のない量で与えてOK。
常識の範囲で、脂っこいものや刺激物は避けましょう。
柔らかいおかゆやうどん、バナナなどが定番ですが、
「少しでも食べたい」という気持ちがあるなら、お菓子などでも構いません。
👉 食べられないより、“少しでも食べられる”ことが大切です。
🔹 嘔吐・下痢の処理と感染対策
- 吐物や便は手袋・マスクをして処理
- 消毒は塩素系漂白剤(アルコールでは不十分)
- 洗濯は分けて行い、しっかり乾かす
- コップやタオルは共有しない
👉 感染予防は“家庭内での二次感染を防ぐ”意識が重要です。
登園・登校の目安
- 嘔吐・下痢が止まり、元気・食欲が戻ったらOK。
- ただし、便中のウイルスはしばらく残るため、家庭内では引き続き手洗いを徹底しましょう。
まとめ
- 子どもの胃腸炎の多くはウイルス性で自然に回復します。
- 抗菌薬は不要で、最優先は脱水の予防。
- 吐き気が落ち着けば、食べられるものを少しずつでOK。
- 食事制限は不要。脂っこいもの・刺激物だけ控えましょう。
- 嘔吐物や便の処理は丁寧に。消毒は塩素系漂白剤で。
- 血便を認めた場合は、細菌性感染や腸重積の可能性があるため、すぐに医療機関へ相談を。
👉 嘔吐や下痢はつらいですが、多くは数日で落ち着きます。
焦らず、水分と休息をとりながらお子さんの“回復力”を信じて見守りましょう。