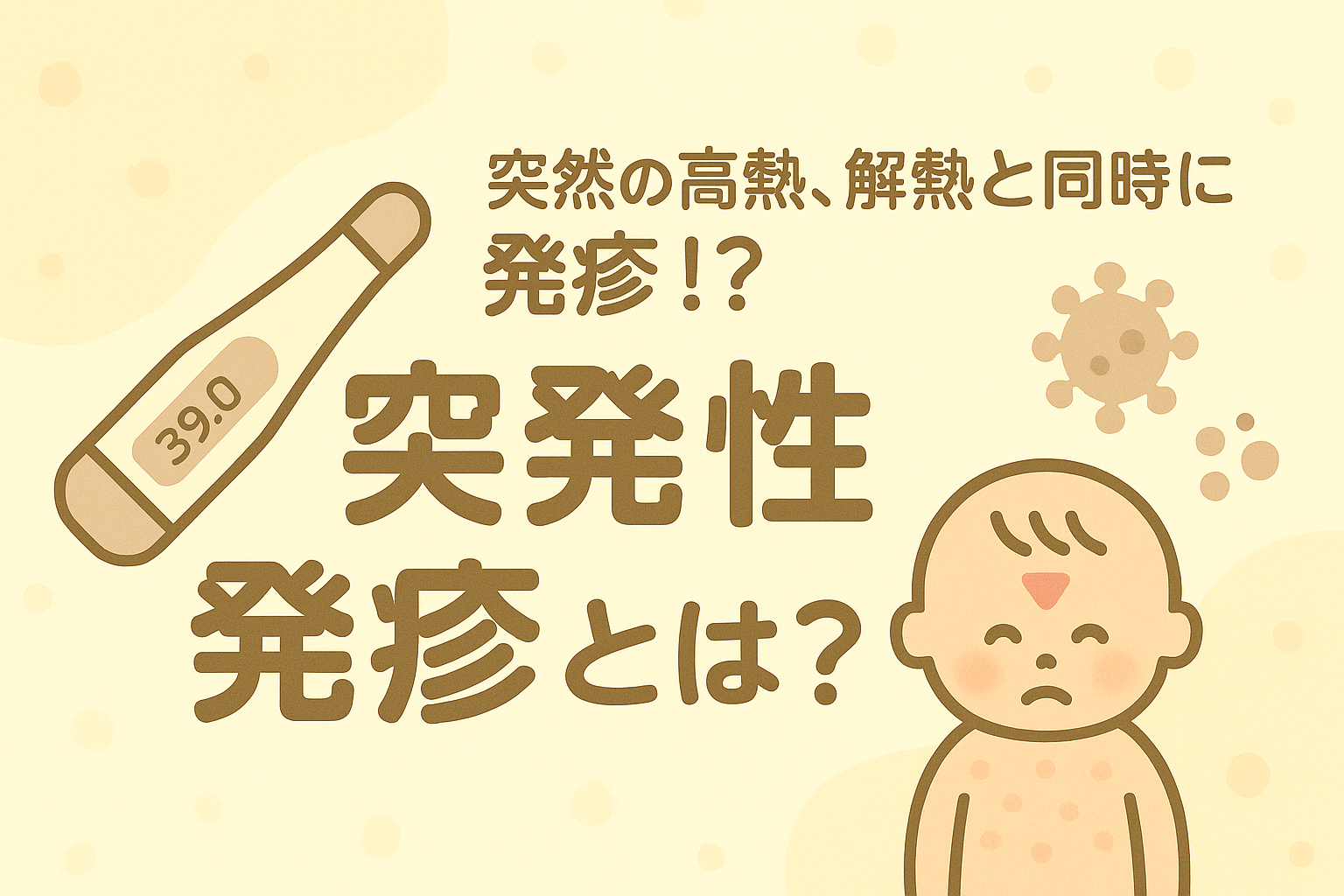はじめに
生後半年ごろから1歳前後のお子さんに多い「突然の高熱」。
3〜4日ほど高い熱が続いたあとに、ようやく熱が下がったと思ったら全身に発疹が……。
このパターンで最も多いのが 突発性発疹(とっぱつせいほっしん) です。
多くのご家庭で「初めての発熱」が突発性発疹であることも珍しくありません。
熱の割に元気があったり、機嫌が良くなったり悪くなったりと、親御さんとしては判断に迷うことも多い病気です。
👉 初めての高熱に焦らずに対応できるよう、特徴や注意点を知っておきましょう。
突発性発疹とは
突発性発疹は、主に ヒトヘルペスウイルス6型(HHV-6B) による感染症です。
生後4か月〜1歳ごろに発症することが多く、2歳までにほとんどの子どもが一度は感染します。
一度感染すると免疫ができ再発はしませんが、ヒトヘルペスウイルス7型(HHV-7) でも同じような症状を示すことがあり、生涯で2回までかかる可能性 があります。
HHV-7によるものはやや年長(1歳半〜2歳以降)で発症することが多いとされています。
👉 赤ちゃんの「初めての発熱」が突発性発疹というケースは非常に多いです。
主な症状と経過
突発性発疹の典型的な経過は次のようになります。
- 突然の高熱(39〜40℃台)が3〜4日ほど続く
- 熱のわりに比較的元気(食欲や機嫌は日によって変動)
- 解熱と同時に、体幹部から顔・四肢にかけて細かい発疹が出現
- 発疹はかゆみが少なく、数日で自然に消失
発疹は赤い小さなブツブツが体幹を中心に広がり、触っても痛がらないのが特徴です。
発疹が出たあとに「やっと元気になった」と感じる保護者も多いでしょう。
👉 「熱が下がったのに発疹が出た」―このタイミングが突発性発疹の大きなヒントです。
診断
突発性発疹は、その**特徴的な経過(高熱 → 解熱 → 発疹)**によって診断されます。
血液検査や迅速検査などで診断することも可能ですが、ほとんどは臨床的に判断されます。
診察では、喉の奥に「永山斑(ながやまはん)」と呼ばれる赤い点状の発疹が見えることもあり、突発性発疹を示唆する所見のひとつです。
また、発疹が出るころには血液中からウイルスが消え、唾液中でもほとんど検出されないとされており、
発疹出現の時期には感染力はほとんどありません。
つまり、発疹が出てからは周囲にうつす心配はまずないと考えてよいでしょう。
👉 発疹が出てきたら「もう治りかけ」と捉えてOK。焦らずに見守りましょう。
治療
突発性発疹は自然に治る病気です。
原因がウイルスであるため、抗菌薬(抗生物質)は不要です。
治療の中心は、つらい症状を和らげる 対症療法 です。
🔸高熱への対応
- 体温が高くてしんどそうなときは、アセトアミノフェンなどの解熱剤を使用
- 水分摂取をこまめに(母乳・ミルク・経口補水液など)
- 元気であれば無理に熱を下げなくても大丈夫
👉 解熱剤は“熱を下げる薬”ではなく“楽に過ごすための薬”。様子を見ながら上手に使いましょう。
🔸食欲がないとき
- 無理に食べさせず、消化の良いものを少しずつ
- 脱水予防を優先(おしっこの回数・量をチェック)
👉 熱が下がると食欲も自然に戻ることが多いです。焦らず様子を見ましょう。
注意が必要な合併症
ほとんどの突発性発疹は軽症で自然治癒しますが、ごくまれに合併症を起こすことがあります。
- 熱性けいれん(5〜10%にみられる)
- 痙攣重積や脳炎・脳症(極めてまれ)
- 肝炎、血小板減少など
高熱時にけいれんを起こした場合は、落ち着いて横向きに寝かせ、呼吸を確保。
迷わず救急要請が必要です。※詳しい対応は過去の記事を参照ください。
👉 高熱によるけいれんは多くの場合一過性。焦らず、安全確保を最優先に。
ご家庭で確認する際のポイント
突発性発疹の発疹は、赤く細かい粒が体幹を中心に広がります。
個人情報や誤認リスクの観点から画像掲載は控えますが、
もし「これかも?」と思った場合は 「突発性発疹」「roseola infantum」 などで画像検索して、お子さんの発疹と比較してみてください。
👉 ただし、少しでも心配であれば自身だけで判断せず、心配な場合は医療機関に相談を。
まとめ
- 突発性発疹は ヒトヘルペスウイルス6型・7型による感染症
- 多くは 生後4か月〜1歳ごろ に発症
- 突然の高熱 → 解熱後に発疹出現 が特徴
- 発疹が出るころには感染力はほとんどない
- 治療は自然経過の観察と対症療法が中心
- 熱性けいれんや脱水に注意
👉 「発疹が出てきた=もう治りかけ」のサイン。焦らず、しっかり見守ってあげましょう。