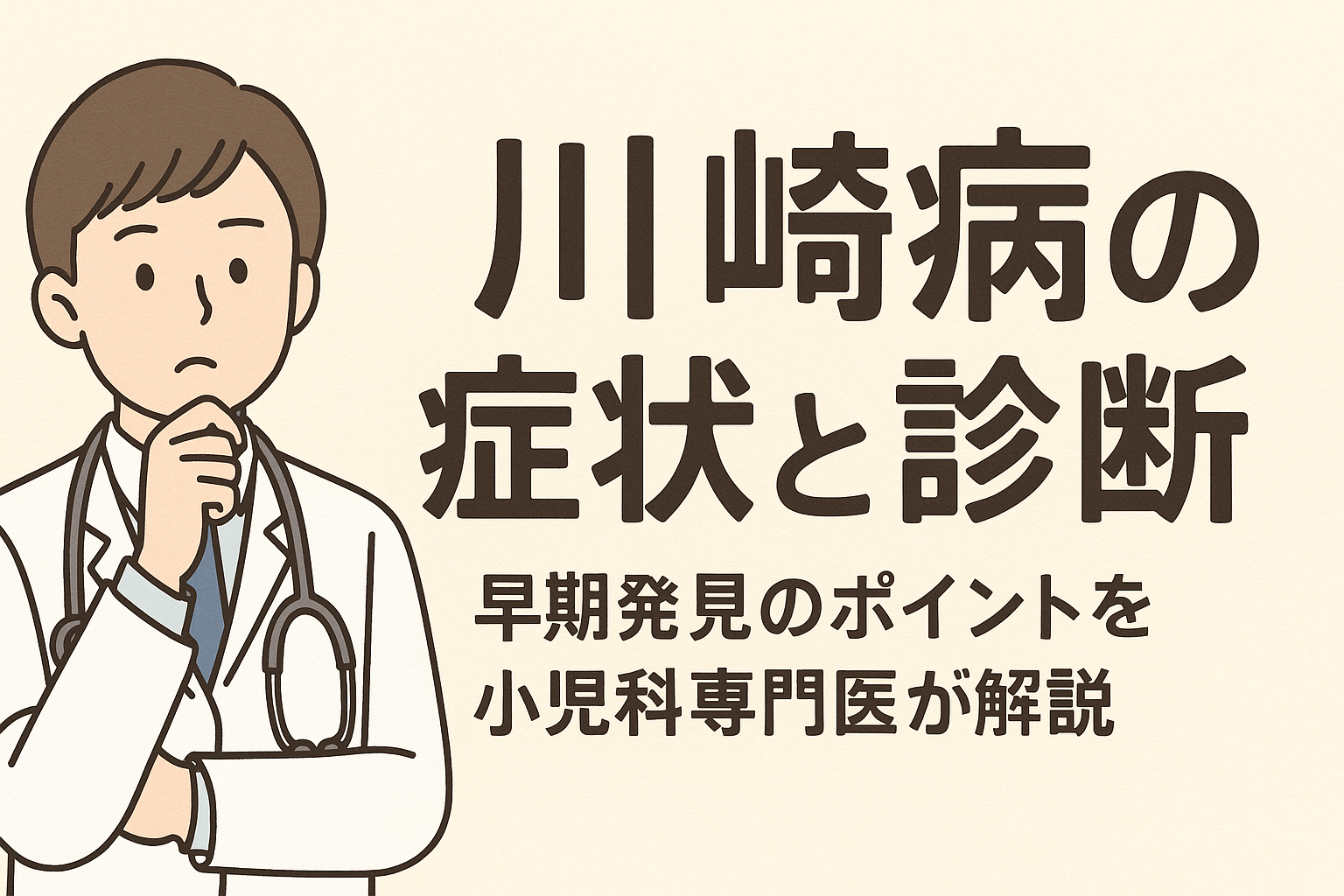目次
はじめに
川崎病は、どれだけ早く診断できるかがとても大切な病気です。
ただし症状はそろって出てこないことが多く、最初の数日は“風邪っぽく見える”こともよくあります。
今回は、川崎病を見逃さないために知っておきたいポイントを、
専門医の視点で分かりやすく整理して解説します。
👉 川崎病は「典型じゃなくても疑う」ことが何より重要です。
親が気づきやすい症状
前回の記事で説明したとおり、川崎病には6つの主要症状がありますが、ここではまず親御さんが気づきやすい症状を紹介します。
① 発熱
- 高熱が続く
- 解熱剤が効きにくい
- 咳、鼻汁症状が乏しい
② 白目の充血
- めやにが少ないのに白目が真っ赤
- 一日中ずっと赤い
③ 唇・口の変化
- 唇が赤くカサカサ
- いちご舌(舌にぶつぶつ)
④ 手足の変化
- 手や足の指先が赤い
- 指先の皮膚が突っ張る感じでテカテカになる(硬性浮腫)
⑤ 発疹
- 蕁麻疹様、小丘疹、紅斑など性状は問わない
- 経過中に一度でもでれば、受診時に発疹が消失していても診断項目に含まれる
⑥ リンパ節の腫れ
- 片側でも両側でもありえる
- 触ると痛がることがある
+ BCG痕の赤み(6項目にはないが特徴的)
- BCG接種部位が赤く腫れる
- 小児科医の間では非常に重要なヒント
👉 「熱+赤み(目・口・手足・発疹・BCG痕)」の組み合わせは川崎病を強く疑うポイントです。
なぜ6つすべて揃わなくても川崎病と診断するのか?
診断基準は「6項目中5項目以上」ですが、現場では
✔ 症状がすべて出揃ってから診断していては遅い
というケースが圧倒的に多いです。
理由は:
- 症状が時間差で出る
- 乳児では症状が弱い
- 発疹が短期間で消えることがある
- BCG痕の赤みなど“典型項目以外”が重要なヒントになる
- 特徴が揃う前に冠動脈の炎症が進むことがある
だからこそ、
“揃うのを待たずに”血液検査や心エコーも含めて総合的に診断する
ことが重要になります。
👉 川崎病は「パズルのピースを揃える病気」ではなく、総合判断で見つける病気です。
心エコー(心臓超音波)でわかること
川崎病が疑われたときに最も重要なのが心エコーです。
心エコーでは:
- 冠動脈の太さ(拡大)
- 血管壁の変化
- こぶ(瘤)ができていないか
- 心臓の動き(心機能)
を確認します。
特に川崎病では、
冠動脈が広がり始めていないかが大きな判断材料となり、
✔ 主要症状が揃っていなくても
冠動脈の拡大があれば治療を開始
という流れになります。
👉 心エコーは「川崎病ではないか?」を判断する最重要検査です。
z-scoreとは?親向けにやさしく説明
冠動脈の太さは、子どもの体格の影響を受けます。
そのため「何mm」だけでは評価できません。
そこで使うのが z-score(ゼットスコア) です。
📌 z-score = その子にとって血管が太いかどうかを示す数字
イメージとしては:
- 標準:z-score 0
- 少し太い:2.0〜2.5
- 太くなっている:2.5以上
- 大きく太い:5以上
という段階です。
「平均よりどれだけ外れているか」を示すため、
体の大きさの違いによる誤差が出ない仕組みになっています。
👉 数字そのものよりも「標準からどれだけ外れているか」を見る指標です。
他の病気との違い
川崎病は、以下のような病気ととてもよく似ています。
- アデノウイルス
- 溶連菌感染症
- 手足口病
- 突発性発疹
- アレルギー・蕁麻疹
- 頸部リンパ節炎
実際には:
✔ 風邪や咽頭炎の様な症状からスタートし、途中で川崎病の形が揃ってくることがある
逆に、
✔ 川崎病を疑って入院したが精査の結果、他の病気だったと分かる
というケースも珍しくありません。
診断は「一瞬」で決まるものではなく、
経過を見ながら慎重に判断する病気です。
👉 川崎病は“似ている病気が多い”ため、丁寧な経過観察が不可欠です。
Q&A — よくある質問
Q.熱は何日続いたら受診?
A.4日目で一度受診を検討。
直前に医療機関に受診していても、ご家族からみて川崎病の症状が揃ってきているのであればその時点で受診。
赤み・発疹・元気のなさがあればもっと早くでOK。
Q.発疹やBCG痕の赤みは重要?
A.とても重要です。
- 発疹は一度でも認めていれば所見として扱う
- BCG痕の赤みは川崎病特有のヒント
👉 「熱+赤み」の組み合わせは川崎病でよく見られます。
まとめ
- 川崎病は症状が揃わないまま始まることが多く注意が必要
- BCG痕の赤みも特徴的な所見
- 心エコーで冠動脈の拡大を確認し治療方針を決定
- z-score は体格に合わせた冠動脈の評価指標
- 他の感染症と症状が似ており診断が難しい事もある
- 早期診断・早期治療が冠動脈瘤の予防に直結する
👉 次回は「川崎病の標準治療」について、実際に病院で行われる治療を専門医の視点で解説します。