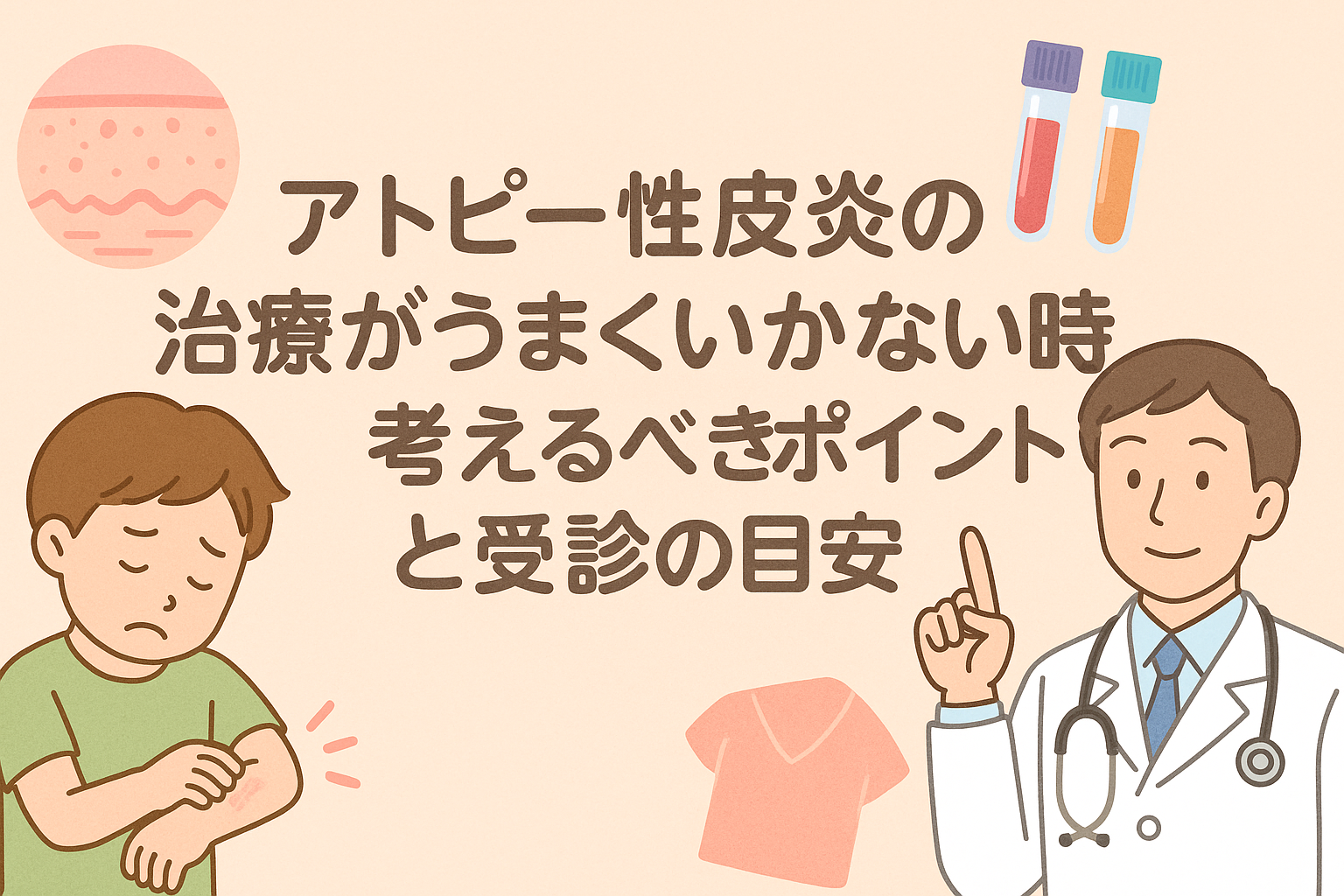これまでの記事では、アトピー性皮膚炎そのものの理解、保湿の重要性、ステロイド・非ステロイド外用薬の使い方、生活の工夫についてお伝えしてきました。
それでも——
「毎日がんばって塗っているのに、ぜんぜん良くならない…」
「治らなくて泣きそうです」
そんな声を外来でよく聞きます。
アトピー性皮膚炎は“日々の積み重ねで改善していく病気”。
だからこそ、うまくいかない時にどう立て直すかがとても大切です。
今回は「治療がうまくいかない時に見直すべきポイント」を、親御さんの不安が軽くなるようにていねいにお伝えします。
👉 “原因さえ分かれば、治療は必ず前に進みます。”
目次
🟤 よくある「治らない理由」トップ5
治療が長引いていると感じる時、多くは次のような“すれ違い”が起きています。
ひとつひとつ整理してみると、改善の糸口が見えてきます。
① 塗る量が足りていない
外来でもっとも多いのがこのパターン。
見た目には塗っているようでも、皮膚に届く量としては不十分というケースが非常に多いです。
・ステロイドは“つるつるの手触りになるまで”しっかり
・保湿剤は“ティッシュがくっつくほどしっとり”
👉 “べたつくくらい”でちょうど良いと思ってください。過去の記事でより詳しく説明しているのでそちらも参考にしてください。🔗過去の記事はこちら
② 塗る期間が短い
赤みが引いた瞬間に治療を止めると、
“見えない炎症”がすぐに再燃し、長引く原因になります。
外来では
「赤みが消えても数日は続けて塗る」
という説明を必ずしています。
👉 “見た目が治ってからが本番”です。
③ 使っている薬が症状に対して弱い
アトピー性皮膚炎は炎症の強弱に合わせて、外用薬の強さも変えます。
・体:強めのステロイドが必要な場合あり
・顔:吸収率が高いため弱い薬で慎重に
・首・肘・膝裏:よく動くため再燃しやすい
弱い薬ばかりだと、炎症を抑えきれず悪化を繰り返します。
👉 外来で“部位ごとの最適な強さ”をもう一度確認しましょう。
④ アドヒアランス(=続けること)が難しくなる
「アドヒアランス」という言葉は聞き慣れないですが、
簡単にいうと**“治療を続けることの難しさ”**です。
・忙しくて夜だけになってしまう
・子どもが嫌がる
・塗り始めるまで重い腰が上がらない
・家族内で塗り方が違う
誰にでも起こりえることです。
👉 一度立ち止まり、できる範囲で治療のリズムを整えることが大切。
⑤ そもそも本当に塗れているか自分では分からない
外来で見ていると
「塗っているつもり」と「実際に塗れている」は全く違う
というケースが本当に多いです。
🟤 私(パパDr)が外来で実際にやっている“治療プランの立て直し”
治療がうまくいかない時、私は次の2つを必ず行っています。
✓ ① その場で“普段通り”の塗り方を実演してもらう
「いつも通りに塗ってみてください」とお願いし、
目の前で実際の塗布方法を見せてもらいます。
・量が少ない
・塗る場所がズレている
・なでるように薄く伸ばしてしまっている
など、気づきが多く、その場で改善点を一緒に確認できます。
👉 “塗り方の癖”は自分では気づきにくいものです。
✓ ② 家にある軟膏をすべて持ってきてもらう
毎回の受診時に
「余っている軟膏を全部持ってきてください」
とお願いしています。
・処方量に対して残量が多すぎる
= → 量・回数が足りていない証拠
・逆にすぐ無くなる
= → 十分に使えているサイン
保湿剤・ステロイドの適切な使用量を客観的に確認できます。
👉 “塗った量の見える化”はとても大切です。
🟤 実は別の病気が隠れていることも
治療しても治らない場合、アトピー性皮膚炎と似た別の皮膚病が隠れていることがあります。
・乳児脂漏性湿疹
・汗疹(あせも)
・カビ(真菌)
・とびひ
・乾癬
・接触皮膚炎(よだれ・マスクなど)
外見だけでは区別が難しい場合も多く、
症状が“典型的なアトピーと違う”時は診察が必要です。
👉 「治らない=アトピーが重症」ではなく、別の原因があることも。
🟤 血液検査(TARC・SCCA2)を行うタイミング
アトピー性皮膚炎の炎症の強さを血液で測定できるのが
TARC と SCCA2 というマーカーです。
親御さんからすると聞き慣れないと思いますが、
これは“アトピーの現在の活動性”を客観的に数値化する指標です。
▷ TARC(Thymus and Activation-Regulated Chemokine)
- 皮膚の炎症が強いほど数値が上がる
- 特に急性の悪化に敏感
- 治療が奏功すると比較的早く下がる
▷ SCCA2(Squamous Cell Carcinoma Antigen 2)
- 炎症が続くと上昇
- 慢性的な湿疹の状態を反映しやすい
- 年齢による基準値の違いが少なく使いやすい
TARCやSCCA2は
皮膚の炎症の強さと比例しやすい指標で、
アトピーの“病勢”を数字で評価できます。
これにより、
・今の治療が適切か
・薬の強さを上げるべきか下げるべきか
・中等症〜重症なのか
などが明確になります。
👉 “見た目では分からない炎症”を数字で把握できるのは大きなメリット。
🟤 皮膚科への紹介を考えるケース
次のような場合、小児科だけでは治療が難しくなることがあります。
- 広範囲の強い湿疹が続く
- 皮膚の感染(細菌・ウイルス感染など)が疑われる
- どの薬にも反応が乏しい
- 重症化して睡眠や日常生活に支障が出ている
- 生物学的製剤(デュピクセントなど)が必要か検討する場合
こういった場合には、皮膚科へ紹介し一緒に加療を考えていく事があります。
👉 “紹介=完全にバトンタッチする”訳ではありません。他の専門領域の先生と協力して、よりよい治療を行っていきます。
🟤 まとめ
- 量・期間・薬の強さなど、治療がうまくいかない理由は多くの場合“調整可能”。
- その場での“塗り方チェック”や“残量チェック”が改善の近道。
- 別の皮膚病が隠れている可能性もあるため、自己判断は禁物。
- TARC・SCCA2は病勢を客観的に知る手がかりになる。
- 必要に応じて皮膚科と連携し、より適切な治療につなげる。
👉 どんなときも“あなたはひとりじゃない”と伝えたいです。ゆっくり、一緒に治していきましょう。