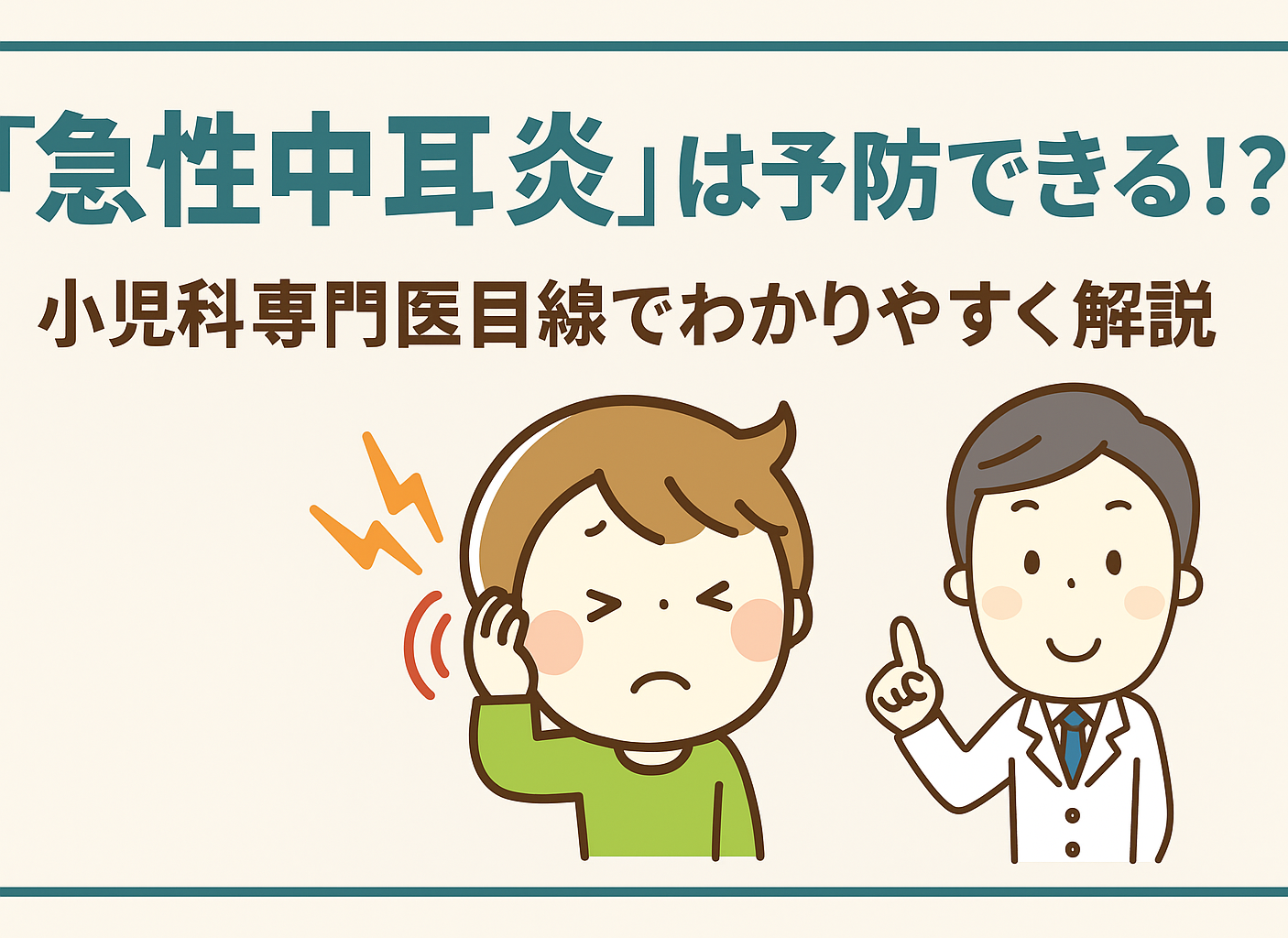🌸 はじめに
お子さんが風邪をひいたあとに「耳を痛がる」「熱がなかなか下がらない」…
そんな経験はありませんか?
その背景にある代表的な病気が急性中耳炎です。
中耳炎というと耳鼻科の病気という印象があるかもしれませんが、
実際には小児科でも日常的によく出会う病気です。
特に1〜3歳の乳幼児では非常に多く、
“子どもの風邪に続く定番トラブル”と言っても過言ではありません。
🦠 急性中耳炎とは?
鼻や喉の奥のばい菌が、耳につながる細い管(耳管)を通って
耳の奥(中耳)に入り、炎症を起こす病気です。
耳の奥に膿や液体がたまり、鼓膜が赤く腫れることで痛みや発熱が生じます。
風邪の経過中、あるいは回復しかけの頃に発症することが多いのが特徴です。
👶 子どもに多い理由
子どもが中耳炎になりやすいのには、きちんとした理由があります。
- 耳管が短く、鼻と耳が近いためばい菌が届きやすい
- 耳管の角度が水平に近く、液体が耳にたまりやすい
- 免疫が未熟で感染を起こしやすい
- 集団保育や兄弟間で風邪をもらいやすい
- 鼻をすすりやすい(鼻水を耳に押し込んでしまう)
👉 鼻をすするクセがある子は要注意!中耳炎は「鼻をかむ」ことで予防できる病気です。
🔍 中耳炎のサイン
子どもは「耳が痛い」と言葉で伝えられないことも多いため、
行動や経過から“サイン”を読み取ることが大切です。
- 発熱が続く
- 一度熱が下がったあと、数日して再び発熱する(鼻水が続いている)
- 耳を気にして触る・いじる
この「解熱後の再発熱+鼻汁の持続」は、
風邪の経過ではなく中耳炎や副鼻腔炎などの二次感染のサインであることがあります。
👉 “熱がぶり返した+鼻水が長い”は、中耳炎を疑うポイントです。
🩺 診断のポイント
中耳炎の診断は、耳鏡を使って鼓膜を観察することで行います。
鼓膜が赤く腫れたり、膿がたまっていたりすれば急性中耳炎と診断されます。
ただし、鼓膜の診察は子どもにとってはちょっと苦手な検査。
泣いたり動いたりすると危険が伴うため、
小児科では全員に耳をのぞくとは限りません。
特に、
- 発熱してまだ日が浅い
- 鼻水があまり出ていない
といった場合には、あえて鼓膜をのぞかず経過をみることもあります。
そんなときに、保護者の方から
「よく鼻をすする」
「最近、耳を気にして触ることが多い」
「以前も中耳炎になったことがある」
「一度熱が下がったのに、また発熱してきた」
といった情報を伝えてもらえると、診察の精度がぐっと上がります。
実際にこうした“親御さんの気づき”が、診断のきっかけになるケースはとても多いです。
👉 診察時に「鼻をすする」「耳を触る」「熱がぶり返した」などを伝えると見落とし防止につながります。
💊 治療方針
2024年改訂の「小児急性中耳炎診療ガイドライン」では、
症状の重さに応じた治療が推奨されています。
🔹軽症の場合
自然に治ることも多いため、抗菌薬を使わずに経過観察します。
痛みが強い場合は、アセトアミノフェンで鎮痛・解熱を行います。
🔹中等症〜重症の場合
細菌感染が強いときにのみ**抗菌薬(アモキシシリンなど)**を使用。
鼓膜の奥に膿がたまっている場合は、鼓膜切開で排膿を行うこともあります。
👉 「中耳炎=抗菌薬」ではありません。必要なときだけ使うのが今の標準です。
🏠 ご家庭でのケア
- 鼻水をためない(鼻をこまめにかむ or 吸う)
- 鼻をすするクセをやめるよう声かけを
- 抗菌薬は指示通りに飲み切る
- 繰り返す場合は耳鼻科と小児科の連携を
👉 鼻のケアが最大の予防。鼻吸いで中耳炎を防げる病気です。
🧸 まとめ
- 急性中耳炎は子どもに多い「風邪の合併症」
- 原因は鼻水のばい菌が耳に入ること
- 鼻をすするクセが発症のきっかけに
- 鼻吸い・鼻かみでしっかり予防できる
- 軽症では抗菌薬を使わないのが一般的
- 熱がぶり返した・鼻水が長い・耳を触るは受診のサイン
- 親の観察が診断のヒントになる
👉 「風邪が長引く」「熱がぶり返した」そんなときは、
中耳炎が隠れていないかチェックしてもらいましょう。