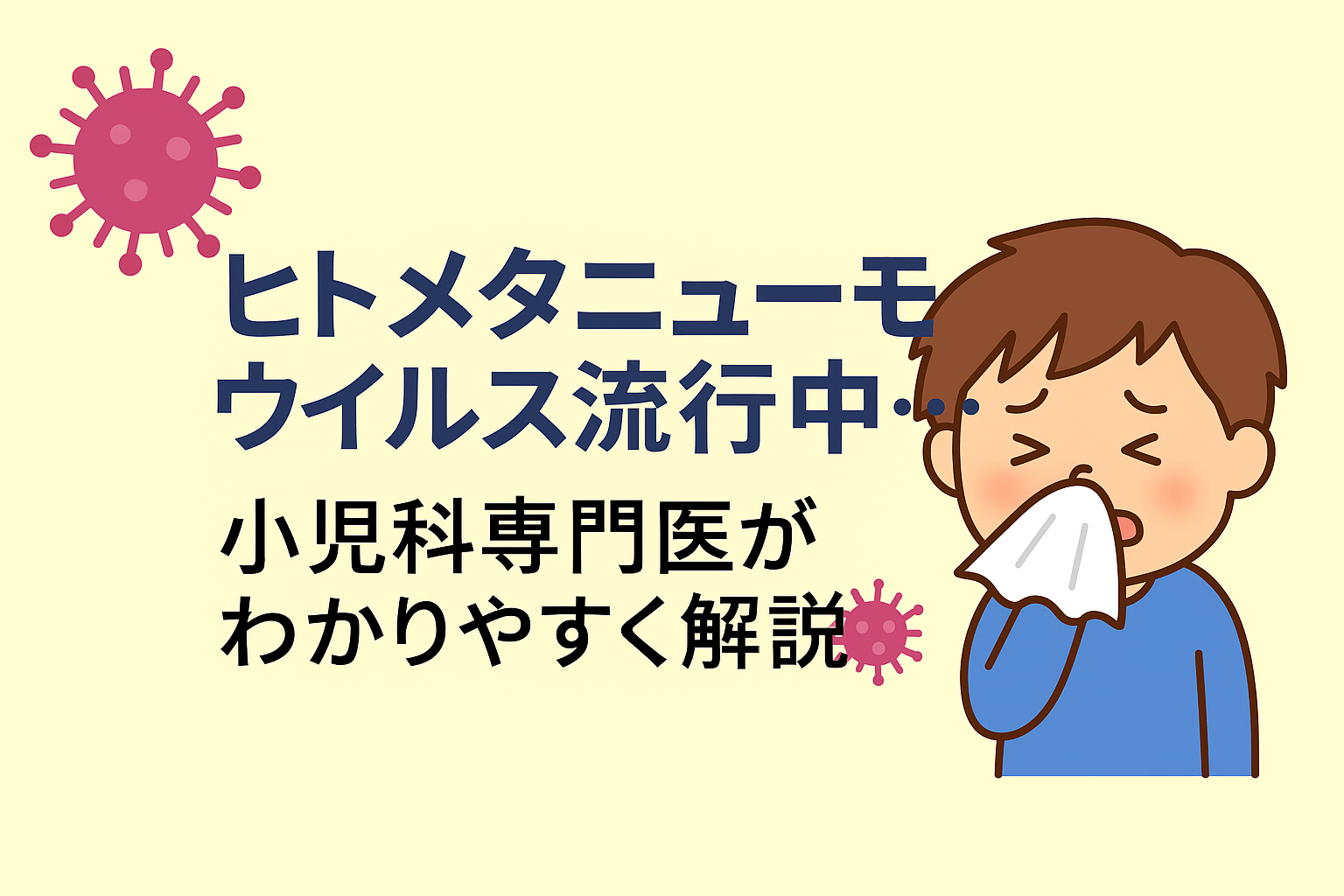🌸 はじめに
春から初夏にかけて流行する「ヒトメタニューモウイルス(hMPV)」。
咳や鼻水で始まり、夜になるとゼーゼーと苦しそうにする——
そんな症状で受診されるお子さんが、最近とても増えています。
もともとは季節性の感染症とされていましたが、
近年ではRSウイルスと同様に“通年性”の傾向を示すようになっており、
一年を通して散発的に流行が見られるようになっています。
👉 「春のRSウイルス」と呼ばれますが、今や季節を問わず注意が必要なウイルスです。
🦠 ヒトメタニューモウイルス(hMPV)とは
hMPVは2001年に発見された比較的新しいウイルスで、
RSウイルスと同じ「パラミクソウイルス科」に属しています。
感染経路は飛沫感染と接触感染で、
家庭内や保育園などでの兄弟間感染が非常に多く見られます。
ほとんどの子どもが2歳までに一度は感染し、
一度感染しても免疫が長く続かないため再感染を繰り返すこともあります。
👉 “RSのいとこ”のようなウイルス。風邪と見分けがつきにくい点も共通しています。
🤧 主な症状
hMPVの症状は風邪に似ていますが、分泌物が多いのが特徴です。
鼻汁や痰が多く、鼻づまりが強くなることで呼吸がしづらくなったり、
ミルクや食事が取りにくくなることがあります。
- 発熱(数日続くことも)
- 鼻水・咳(時間がたつほど強くなる)
- ゼーゼーとした呼吸音(喘鳴)
- 食欲低下・元気がない
- 乳児では呼吸困難や肺炎に進行することも
とくに乳幼児では、呼吸が荒い・哺乳ができないといったサインがある場合、早めの受診が必要です。
👉 “鼻や痰が多い風邪”は要注意。呼吸のしづらさが重症化のサインです。
🔬 診断
RSウイルスとhMPVは症状がよく似ているため、
医療機関では「抗原迅速検査」や「PCR検査」により判定します。
複数のウイルスを同時に調べる検査キットもあり、
発熱や咳が長引く場合にはhMPV感染を疑って検査することがあります。
💊 治療
特効薬やワクチンは現在のところ存在しません。
そのため、治療の基本は「対症療法」と「家庭でのケア」です。
- 解熱剤(発熱がつらい場合に)
- 去痰薬・吸入(痰や咳を和らげるため)
- 酸素投与・点滴(呼吸状態が悪い場合)
- 水分補給(脱水防止)
hMPVは鼻汁・痰といった分泌物が非常に多くなるタイプの感染症です。
このため、鼻づまりが強いときは「鼻をかむ」ことが大切。
まだ自力でかめない子は、鼻吸い器などで積極的に吸ってあげると、呼吸も楽になります。
👉 鼻をすっきりさせるだけで、ミルクの飲みやすさも呼吸の安定も全く違います。
🏠 ご家庭でのケアポイント
- 鼻づまりがあるときは、食事や授乳前に鼻を吸う
- 寝る姿勢を少し起こすと、咳やむせ込みが軽減
- 水分をこまめに補給し、脱水を防ぐ
- タオル・食器は共有しない(家族内感染予防)
- 夜中に呼吸が苦しそうなときは、無理せず早めに受診
また、RSの記事でも述べましたが、
hMPVも鼻や喉の分泌物が多くなるタイプのウイルス感染症です。
対応やケアのポイントはRSと共通する部分が多いため、
ぜひ「RSウイルス感染症の記事」も併せて参考にしてみてください。
👉 “鼻づまりケア”はどの呼吸器感染症でも基本中の基本です。
🩺 まとめ
- hMPVはRSウイルスと同じグループの呼吸器ウイルス
- 近年では季節を問わず通年性の流行が見られる
- 鼻汁・痰が多く、呼吸が苦しくなりやすい
- 治療は対症療法が中心。呼吸と水分の見守りが大切
- 鼻をかむ、または吸ってあげることが重要なケア
👉 “鼻づまりのケア”がhMPV対策の第一歩。
焦らず、呼吸と元気さを見守ってあげましょう。